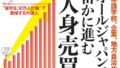グローバリズムの蜜月は終わりを告げようとしています。
米国発のグローバル化は、世界経済に大きな恩恵をもたらした一方で、格差の拡大や国家主権の弱体化といった副作用も生み出しました。
今、世界は分断の時代を迎え、日本は複雑な選択を迫られています。
本記事は、京都大学大学院准教授 柴山桂太氏の解説を基に、私たちが備えるべき経済転換時代のシナリオを読み解きます。
グローバリズムとは何か?「帝国の論理」という視点
柴山氏は、グローバリズムを単なる経済的な現象として捉えるのではなく、「帝国の論理」という視点から掘り下げています。これは非常に重要な指摘です。
グローバリズムは、一見すると自由貿易や国際協力のように見えますが、実際には、特定の国(主にアメリカ)の経済的・政治的な影響力を世界中に拡大する手段として機能してきた側面があります。

アメリカ主導のグローバリズムは、冷戦終結後の「歴史の終わり」という楽観的なムードの中で加速しました。しかし、2008年のリーマンショックや、その後のトランプ政権の登場によって、その限界が露呈したのです。
トランプ大統領の「アメリカ・ファースト」政策は、グローバリズムへの明確な反旗であり、世界経済の分断を加速させました。
なぜ日本はアメリカと同じ道を辿ってしまったのか?構造的な問題
日本は、戦後の高度経済成長期において、アメリカの経済モデルを積極的に取り入れました。その結果、日本経済は大きく発展しましたが、同時に、アメリカの影響を強く受ける構造が固定化されたのです。
バブル崩壊後、日本は「失われた20年」と呼ばれる長期的な不況に苦しみましたが、その原因の一つは、グローバリズムへの過度な依存にあると言えるでしょう。
日本は、アメリカの金融政策や貿易政策に振り回され、自国の経済主権を十分に確立することができませんでした。また、グローバル化の波に乗るために、国内産業の空洞化や労働市場の流動化を進めた結果、格差が拡大し、社会の安定が損なわれたのです。
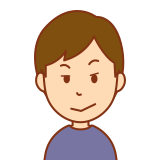
拝米主義が招いた思考停止の政治(-_-;)
分割するグローバル経済秩序…日本が備えるべきシナリオ
現在、世界経済は、アメリカを中心とする陣営と、中国を中心とする陣営に分断されつつあります。日本は、どちらの陣営につくのか、あるいは独自の道を歩むのか、難しい選択を迫られています。
柴山氏は、日本が様々なシナリオに備えるべきだと強調します。具体的には、以下のような対策が考えられるでしょう。
- 国内経済の強化: グローバル経済の変動に左右されない、強靭な国内経済を構築する。そのためには、中小企業の育成や地方経済の活性化が不可欠。
- 技術革新の推進: AIやロボットなどの先端技術を積極的に導入し、生産性を向上させる。これにより、人手不足の解消や賃上げにつながる可能性がある。
- 社会保障制度の充実: 格差の拡大を防ぎ、社会の安定を維持するために、社会保障制度を充実させる。具体的には、年金制度の改革や生活保護の拡充などが考えられる。
- 外交戦略の再構築: 特定の国に依存するのではなく、多様な国との関係を構築する。そのためには、独自の外交戦略が必要となる。
これらの対策は、決して簡単なものではありません。しかし、日本がグローバル経済の激動期を乗り越え、持続可能な社会を築くためには、避けて通れない道だと言えます。
まとめ
柴山桂太氏の解説は、グローバリズムの光と影、そして日本が抱える構造的な問題を浮き彫りにしました。
日本は、グローバル化の恩恵を受けつつも、その負の側面を克服し、自国の経済主権を確立する必要があります。そのためには、国内経済の強化、技術革新の推進、社会保障制度の充実、外交戦略の再構築など、多岐にわたる対策を講じる必要があります。
より深く理解するためには、動画を視聴をおすすめします。
出典:【世界経済の優等生 日本】京大院准教授が明かす!「反グローバリズム」って何?/グローバル化は善か悪か/日本人が絶対に備えるべき経済転換時代のシナリオ(京都大学大学院准教授 柴山桂太)【ニュースの争点】

「反グローバリズム」という切り口で思考すれば、あらゆる問題がつながりますよね?