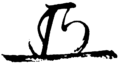新嘗祭は、「にいなめさい」と読みます。
誰も教えてくれないから、読めもしないし、なんのこと?という感じですよね。
新嘗祭とは、その年の収穫に感謝して新穀を神様にお供えし、来年の豊穣を願う行事です。
「にいなめのまつり」「しんじょうさい」と呼ぶこともあります。
日本書紀にも登場するほど古くから行われてきた行事で、現在では全国各地の神社で11月23日に行われています。
でも、11月23日は、「勤労感謝の日」という国民の祝日ですよね?
なぜ同じ日が「勤労感謝の日」なのか?という疑問がわきます。
本記事はその理由についてです。

新嘗祭「にいなめさい」とは?
新嘗祭を理解するには、「祈年祭(きねんさい)」という行事も知っておいたほうがよいでしょう。
祈年祭(きねんさい)
祈年祭(きねんさい)は、春の田植えを行う前に、五穀豊穣を祈るお祭りです。
「としごいのまつり」とも呼ばれます。「とし」とは稲の美称であり、「こい」は祈りや願いで、お米を始めとする五穀の豊かな稔りを祈ることを意味します。

祈年祭は、毎年2月17日に行われます。
にいなめさい
春の耕作始めに行う「五穀豊穣」を祈るお祭りに対して、新嘗祭は、「新」は新穀を「嘗」はお召し上がりいただくことを意味しており、収穫された新穀を神に奉り、その恵みに感謝し、国家安泰、国民の繁栄をお祈りするお祭りです。

神宮
下記は、伊勢神宮のサイトにある「祈年祭と新嘗祭」の説明です。
現在、このお祭りは毎年11月23日に宮中を始め、日本全国の神社で行われていますが、特に宮中では天皇陛下が自らお育てになった新穀を奉るとともに、御親らもその新穀をお召し上がりになります。収穫感謝のお祭りが11月下旬に行われるのは全国各地での収穫が終了する時期に、御親祭を行われたためと考えられています。
引用元:神宮 恒例祭典 祈年祭・新嘗祭
日本人にとって、米というものが如何に大事で神聖なものか、ということがよくわかりますね。
勤労感謝の日
11月23日は、「勤労感謝の日」という国民の祝日です。
でも、この名称が決まった背景を知ると愕然としますよ。。🤣🤣
祝祭日の選定し直し
戦後、日本国憲法が制定され、祝祭日から国家神道の色彩を払拭するという方針のもと、新たに祝祭日を選定し直すことになったのがきっかけです。
「感謝の日」案
国会(衆議院)で、新嘗祭が新穀の収穫に対する感謝の日であることから、それに代わる名称として「感謝の日」案が有力となりました。
米国のThanksgiving Dayが由来
当時の官僚の話によれば、GHQの命令により、米国のThanksgiving Dayに相当する祝日を設けることになった、というのが由来の実態のようです。(-_-;)
賛成多数で「勤労感謝の日」が採択
「感謝の日」では漠然としており、何に対する感謝かさっぱりわからない?ということで、「勤労感謝の日」と「労働感謝の日」の二つの案が出され、日本社会党などの賛成多数で「勤労感謝の日」が採択されました。
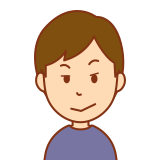
「感謝する」という意味では同じでも、その対象となるものが全く違うって、意味なくねぇ?
まとめ
昭和22年の皇室祭祀令廃止により、新嘗祭という表記の「祭日」はなくなりました。
他の国民の祝日にも、新嘗祭と同じように名称が変わったものがあります。

「日本を取り戻す」ためにも祭日表記の復活を願いたいものです。